デザイン部でチーフマネージャーを務めている御幡です。
今回は、弊社が推進している「空間DX」についてお話ししようと思います。
「空間DX」をわかりやすく整理しながら、それが僕たちデザイナーにどんな可能性をもたらすのかをご紹介します。
空間DXは“新しいメディア表現”

まず強調したいのは、「空間DXは従来のデザイン表現と断絶した存在ではない」という点です。新しい概念が登場すると戸惑いもありますが、それはこれまでの表現が終わるということではありません。むしろ積み重ねてきたものを次の形にアップデートしていくチャンス、それが空間DXだと考えています。
たとえば写真が登場したとき、絵画が不要になったわけではありません。映像が広がっても写真は残り、互いを補完しながら新しい表現を生み出してきました。インターネットが普及してWEBが浸透したときも、インタラクティブ体験が登場したときも同じです。
表現を整理すると次のようになります。
- 写真:瞬間を切り取る
- 映像:時間の流れを伝える
- グラフィックデザイン:情報を整理し、視覚的に伝える
- WEB表現:双方向性を加える
- インタラクティブ体験:体験者が主体となって関わる
- 空間DX:空間そのものがメディアになる
つまり空間DXは、従来のメディアを包含した「次のメディア表現」なのです。
体験価値が求められる時代へ
ではなぜ今、空間DXなのでしょうか?
理由はシンプルで、「人々が求める価値が“モノ”から“体験”へとシフトしている」からです。
モノがあふれる現代では、ただ所有するだけでは差別化が難しくなっています。その代わりに人々の記憶に残るのは「どんな体験をしたか」という感覚的な価値です。旅行やイベントをSNSで共有するのも、体験そのものが社会的な意味を持つからだと思います。
空間DXはまさにそのニーズに応える表現であり、空間全体をメディアとしてデザインすることで、ユーザーは五感を通じて没入し、心に残る体験を得ることができます。これは映像やWEBだけでは到達できない価値のレイヤーなのではないでしょうか?
つまり空間DXは「メディアの進化」であると同時に「体験価値の深化」でもあるのです。
LBEという新しい文脈
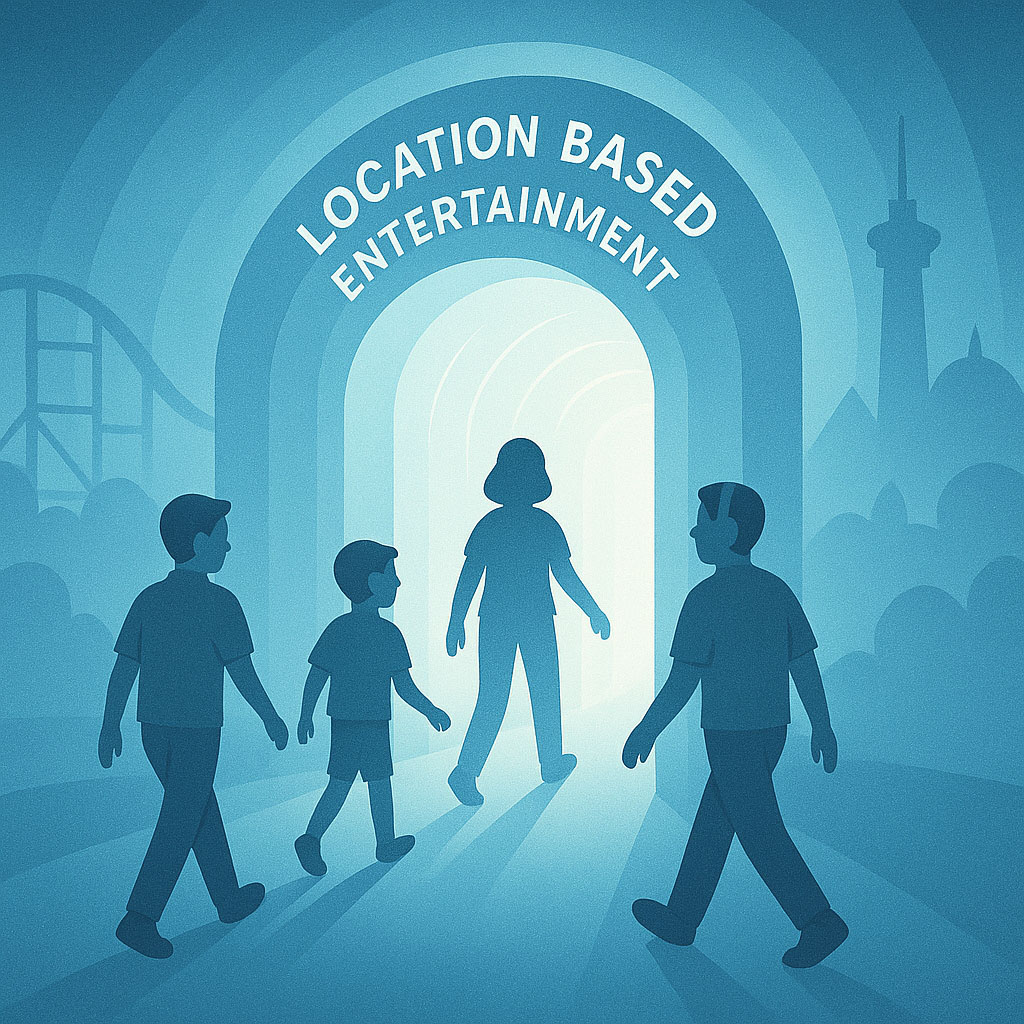
ここで「LBE(Location Based Entertainment)」にも触れておきたいと思います。これは「特定の場所に行かなければ体験できない、インタラクティブで没入感のあるエンターテインメント」を指します。
テーマパークやVR体験施設などが代表的で、ディズニーランドのアトラクションもその一例です。まさに“空間がメディア化した体験”だと言えます。
重要なのは、この流れがエンターテインメントにとどまらず、商業施設や企業のショールーム、さらには街づくりにまで広がりつつあることです。ブランドの世界観を空間で体験させることが、商品や広告以上に強力なコミュニケーション手段になり始めています。
デザイナーに求められるのは「掛け合わせの力」

では空間DXにおいて、デザイナーに求められるものは何でしょうか。
僕は「掛け合わせの力」だと考えています。
空間を体験として設計するには、一つの専門スキルだけでは不十分です。映像、音楽、照明、建築、インタラクションデザイン、グラフィック…。それぞれの特性を理解し、統合していく力が必要です。つまり特定分野のエキスパートである以上に、ジャンルを横断して会話できる能力が重要になってきています。
幸いにも僕たち1-10の環境には多様なスペシャリストが揃っています。映像に強い人、グラフィックに強い人、空間デザインに長けた人。これらの力をどう組み合わせて最大化するかが、アートディレクターやデザイナーにとっての新しい挑戦であり、成長の機会になるのではないでしょうか。
つまり新しいスキルをゼロから覚えるだけではなく、今ある自分のスキルをどう空間DXに活かせるか、どう掛け合わせられるかという視点が大切なのです。
空間を構成するすべてがメディアになる
さらに空間DXでは、「何をメディアと捉えるか」という視点が大きく広がります。
従来はスクリーンや照明といった明確な演出装置が中心でした。しかしこれからは空間を構成するあらゆる要素が表現の一部となり得ます。
什器や造作が動いたり光ったりする。床や壁そのものがインタラクティブな情報を発信する。さらには香りや音響までが体験を形づくる要素になる。
つまり空間DXとは、スクリーンの外に広がるすべてをメディアと捉え、空間そのものが「語りかけてくる」体験を設計することなのです。
空間DXはデザイナーにとって新しいキャンバス

空間DXは、これまでの表現を捨てて全く新しいことをするものではありません。むしろ、私たちが培ってきたスキルや感性をより広いフィールドで活かせる「新しいキャンバス」だと言えます。
写真、映像、グラフィック、WEB、インタラクティブ体験といった表現がそうであったように、空間DXもまたその延長線上にあります。そして、その中でデザイナーが果たす役割は、これまで以上に挑戦的で面白いものになると考えています。
デザイン部としても、新しい表現の可能性を信じて、仲間たちとともに空間を「体験のメディア」として育てていきたいと思っています。
